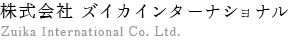ホテルグランフェニックス奥志賀ができるまで
《田島和彦自伝》
19. 帰国のあとさき
こうしてヨーロッパでビジネスの修業をしている間、2回にわたって私に会いに来てくれた方々がいた。伊勢丹の小菅丹治さんと、山中鏆さんだ。小菅さんは伊勢丹創業家の辣腕で知られた3代目、山中さんはのちに松屋や東武百貨店の社長を務めて“百貨店経営の神様”と言われるようになった人だ。その2人が、もちろん商用があってヨーロッパを回るついでとはいえ、「伊勢丹に入らないか」とわざわざ足を伸ばしてくれたのだ。「新しい会社を立ち上げるので、加わってほしい」と。伊勢丹には兄が務めていて、父も商売を通じて小菅さん、山中さんには知遇があった。
会社の経営陣が2年続けて訪ねて来てくれるなど、身に余る出来事だ。自分の人生のなかで、それほどまでしてくれた人があるだろうか。卒業したてのまだ何もできない若僧を招いてくれたヘンスリー社の社長には大いに恩義を感じていたから、辞めると言うのは本当に心苦しかったが、いつかは日本に帰らなければならない。社長には事情を話して、約5年の海外生活にピリオドを打ち、帰国することになった。
行きは船だったが、帰りは飛行機だ。
実は当初、フォルクスワーゲンで大陸横断して日本まで帰ってやろう、と目論んでいた。ところがパキスタンとインドの間に盗賊が出没して殺される人が出たという情報が入ってきた。さらに、カンボジアが洪水で、船でないと行けない、非常に危険だという。
残念だったが、あきらめた。
以前とは違い、冷静に物事を見極める自分がそこにいた。
ヨーロッパに来て私自身の山へのスタンスも以前とは変わってきていた。四季で移り変る山の風景に親しみ、トーマス・マンの小説『魔の山』を読んで、人によっては素晴らしい山が、苦しく逃げ場のない状況を象徴する存在になることも知った。ただ登る対象、挑戦するものとしてではなく、山という存在そのものに関心が広がった、とでも言おうか。
余談となるが、小説では日本の作家である横光利一がヨーロッパのことを書いた『旅愁』も、繰り返し読んだ。自分のいるスイスが登場することもあり、同じ日本人として文化の違いに悩む主人公の姿を興味深く感じたものだ。
なにより以前と変わったのは、今や自分にとって挑戦すべき別の山、ビジネスという山が目の前にそびえていたことだ。ヨーロッパでさまざまな見聞を積み、仕事や交友を広げ、パブリックな人間として成長して、ビジネスの世界で羽ばたける自分、挑戦できる自分を自覚していた。そんな素晴らしい山を目の前にして、無謀な冒険はできなかった。
帰国便に乗る時には、さすがに感慨が胸に迫った。
当時スイスから日本への航空便は、チューリヒの空港から12時50分発の一便だけが飛んでいた。この5年の間、会社への来訪者の送迎にチューリヒの空港には足しげく通ったが、TOKYO行き12時50分発の表示を眺めながら、何度「これに乗れば帰れるんだな」と思ったことだろう。苦しかった時、壁にぶつかった時、そして岐路に立った時……。しかし「ここで乗ったら、俺は終わりだ」と帰ることを選ばなかった自分がいた。
5年という歳月を経て帰っていく日本。そこでどんな挑戦が待ち受けているのか、期待と意気込みを胸に、ヨーロッパでの武者修行時代は幕を閉じた。
こんな貴重な経験ができたのも、父のおおいなる理解と支援があったからこそだと、今になって思う。