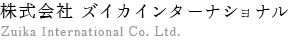ホテルグランフェニックス奥志賀ができるまで
《田島和彦自伝》
7. 滑落、死に一番近づいた瞬間
自分にとって生命の危険を感じたという点では、同じく大学時代、今度は私が先輩として後輩部員を引率した時の経験が一番かもしれない。
冬の終わりの立山から穂高へ、部員6~7人を引き連れての縦走コースだったが、歩き始めてすぐ、目の前にかなりの悪場が現れた。そこで、まず自分が先行して現場の様子を見なければと思い、部員を留めて歩いていったのだが、知らずに岩場と雪庇の間に立ってしまったのだ。
私自身の体重に加え、背負っていたキスリングは60kgもの重さだったから、ひとたまりもない。足元の雪庇は一気に崩れ、たちまち仰向けに滑落すると、平均斜度40度は超えていただろう斜面をそのまま猛スピードで滑り落ちていく。滑落の場合、25m以内で止められなければ、自分で止めることは不可能と習っていたし、仰向けで頭を下にした状態は最悪とわかっていたので、とにかくなんとかしなければ……と体を振ってみたところ、今度は60kgの荷物の重さが幸いして、滑りながらも腹ばいの体勢になることができた。おまけに、キスリングの横腹が岩に当たった勢いで全身がクルリと180度回転し、頭が上を向く姿勢になっている。さっきよりは、よほどましだ。
気がつくと、手にはピッケルがしっかりと握られている。訓練の際に「ピッケルバンドは必ず手首に通しておけ」と教えられていたのを守っている自分に感心したが、生命の危機に瀕しながらそんな風に思えるほど、妙な余裕があったのは驚きだ。とにかくスピードを落とそうと、ピッケルのブレードを雪面に叩きつけたが、3~4回繰り返してもなかなか速度はゆるんでくれない。そんな時、訓練で腹の下にピッケルを構え、ブレーキにしなければならないと教わったのを思い出し、その構えのまま雪面にブレードを突き立てたところ、60kgのキスリングの重さもプラスに働いて、ようやく滑落を止められた。
「ああ、助かった……」
その喜びにホッとして後ろを振り返ると、ほんの50mほど離れた斜面の先は、はるか黒部渓谷へと落ち込む絶壁になっている。まさに危機一髪の命拾いに、全身からドッと汗が噴き出した。
その間、ほとんど数十秒という短い時間だったが、これほどまで死に近づいた経験はほかにない。滑り落ちてきた斜面を必死で上っていき、雪でびしょ濡れになった様子をいぶかしむ部員たちには、必要以上に不安にさせないよう「景色のいい所で水浴びをしていた」と、おかしな言い訳をしたように思う。雪山において雪庇に乗ることの怖さを、身をもって知る心地がしたものだ。