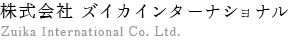ホテルグランフェニックス奥志賀ができるまで
《田島和彦自伝》
2. 私のスキーこと始め
私が中学生の頃、まだ学生時代の猪谷千春さんが東京の私の家から高校・大学へ通っていて、私のベッドの隣に一緒に寝ていた。彼は毎日学校から帰ってくると、代々木にあったワシントンハイツ(在日米軍の兵舎・家族用居住施設)に行って、働きながら英語を勉強していた。当時は、猪谷さん自身、その勉強が未来のドラマチックな展開につながるとわかっていたわけではないが、それでも続けたことが素晴らしかったのだと思う。人は誰しも結果が見えることには努力をするが、まだ見えない将来へ向けて頑張ることはなかなかできるものではない。
結果、そのことが、ヨーロッパへ渡った折に役立ち、AIU保険会社創業者のコーネリアス・バンダ―・スター社長の心をつかみ、彼自身の人生を大きく変えることになる。ダートマス大学へ進み、専門的なトレーニングを積んだことで、コルティナ・ダンペッツォ五輪の回転競技で銀メダルを獲得。のちには、国際オリンピック協会で副会長を務められたが、そうした輝かしい業績も、すべて学生時代のかくれた努力が出発点だったのであり、そのことは私にとってものちのち大きな教訓となった。
このような縁で、子どもの頃の私は猪谷さんにスキーを教わったこともあるが、やはり天才と凡人では大きな違いがある。天才肌の千春さんには、そもそもなぜ私が曲がれないか理解できなかったようだ。「なんで曲がらないの?」と私ではなく、千春さんの方が首を傾げていた。
結局、どうやって曲がるかは、ゲレンデのパトロールをやっている人で「この人の滑りがいいな」と思う人がいたので、そのやり方を真似して覚えた。どうやら、まずスーッとまっすぐに行き、次に体を内向きに倒せば自然に曲がっていくらしい。とはいえ、真似をしてもそう簡単に曲がれるものではない。曲がれずに転んだり、まっすぐ行ってしまってはキックターンする繰り返しだ。今でいえば体重を谷側の足にかければいいということなのだが、そうしたメソッドもまだなく、とにかく倒せば曲がるのだからと、続けてやってみるほかない。かなりの斜面だったが降りきったらまた上って滑り、ターンに挑み続けること34回目、初めてスーッと曲がることができた。
もちろん曲がれたことも嬉しかったが、大事なのは34回続けたことだ。転んでも転んでもあきらめずにチャレンジする。継続することで進歩があると学べたことは、大きな収穫だった。
この数年後には、杉山進さんが全日本で優勝。それを見ていた私の父は、杉山さんにも猪谷さんのような名選手になってもらおうと、東京での生活スタイルを組み、一家総出で応援することにした。こうして、彼もまた私のベッドの横に寝起きするようになった。杉山さんはその後、猪谷さんと共にめでたくコルティナ・ダンペッツォ五輪に出場を果たされた。
この時代のスキー事情は、今の人からは想像もつかないだろう。当時はまだ日本はアメリカの占領下で、志賀高原丸池のゲレンデの半分は進駐軍専用。真ん中に綱が張ってあって、その左側が日本人用になっていた。ゲレンデを整備する圧雪車なんてものもないから、朝起きると他の人とも協力しあって、雪をスキー板で踏んで固めて滑りやすい斜面を作ることから始めるのだ。それ以前に、志賀高原まで来ること自体が大仕事だった。初めの章で書いたとおり、上林から歩いて5時間。途中には相当にきつい坂もある。
当時の志賀高原には、それでもスキーをやりたい、スキーが好きだという人たちだけが来ていた。志賀高原ホテルは終戦直後は進駐軍に接収され、その後、日本に返還されて、画家の岡本太郎さんとかグラフィックデザイナーの亀倉雄策さん、赤井電機の社長の赤井さんといったそうそうたる方々はそちらに滞在していたが、他はみんな丸池ホテルやそれ以外の宿泊施設だ。志賀高原ホテルには時々遊びに行ったことがあったが、ある時、岡本さんや亀倉さんの目に留まって、「君たちは、これからの日本をどうしようと思ってるんだ?」と30分あまりも説教されるはめになった。今思えば、大切な時間を費やして他人の子どもを教え諭してくれたわけだから、ありがたい話だ。
5時間かけてスキーをしに来るという情熱を共有していたからだろうか、今思えば少年だった私を含めて、ゲレンデの人々の間には一体感のようなものがあったように思う。来ている人たちの数も限られていたし、素人に対する指導メソッドやスクールといったものもなかったが、いろいろな世代の人たちと一緒に過ごすこの時間は、まだ子どもだった私が、大人の世界に触れる貴重な体験。それ自体が学校以上の、素晴らしい勉強の場だったと思っている。